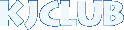2024л…„, н•ңкөӯмқҳ нҢқ мқҢм•…мһҘлҘҙм—җ мһҲм–ҙм„ңмқҳ J-POPмқҳ нҷңм•ҪмқҖ лҲҲл¶Җм…ЁлӢӨ.imaseмқҳ гҖҢNIGHT DANCERгҖҚ, YOASOBIмқҳ гҖҢм•„мқҙлҸҢгҖҚмқҙлқјкі н•ҳлҠ” 2кіЎмқҳ л©”к°Җ нһҲнҠём—җ мқҳн•ҙм„ң J-POPлқјкі н•ҳлҠ” м•„нҠёлһҖнӢ°мҠӨк°Җ л¶ҖмғҒн•ң 2023л…„м—җ мқҙм–ҙ, мһ‘л…„мқҖ мқјліёмқҳ мқҢм•…мқҙ ліҙнҺём Ғмқё кё°нҳёмқҳ н•ҳлӮҳлЎңм„ң мҷ„м „н•ҳкІҢ м •м°©н•ң н•ҙк°Җ лҗҳм—ҲлӢӨ.к·ё л°°кІҪм—җлҠ”, 1л…„мқ„ нҶөн•ҙм„ң нҷңл°ңн•ҳкІҢ к°ңмөңлҗң мҷҖ н•ңкіөм—°мқҙ мһҲм—ҲлӢӨ.к·ё мӨ‘м—җ нҠ№нһҲ мғҒ징м Ғмқё мқҙлІӨнҠёлҘј 3к°ң м •лҸ„ л“ лӢӨл©ҙ, н•ңкөӯмІҳмқҢмқҙ лҗҳлҠ” J-POP л©”мқёмқҳ нҺҳмҠӨнӢ°лІҢ гҖҢWONDERLIVET 2024гҖҚ, 2мқјк°„мңјлЎң 2л§Ң 5,000лӘ… лӮЁм§“мқҳ кҙҖк°қмқ„ лҸҷмӣҗн•ң YOASOBIмқҳ мҷҖ н•ңкөӯм—җ к°Җм„ён•ҳкі , нӣ„м§Җмқҙн’Қмқҳ кіөм—°мқҖ м ңмҷён• мҲҳ м—ҶлӢӨ.к·ёлҠ” мқјліёмқҳ м•„нӢ°мҠӨнҠёлЎңм„ң мІ« кі мһҗлҸ” кіөм—°мқ„ мӢӨнҳ„н•ҙ, J-POPк°Җ н•ңкөӯмқҳ мқҢм•… 씬м—җ лҢҖн•ҙ мқјм •н•ң к¶ӨлҸ„м—җ мҳӨлҘё кІғмқ„ лӘ…мӢӨ кіөнһҲ лӮҳнғҖлӮҙ ліҙмҳҖлӢӨ.
мқҙм ң мҷҖм„ңлҠ” л„җлҰ¬ м•Ңл Ө진 мӮ¬мӢӨмқҙм§Җл§Ң, к·ёлҠ” YouTubeлЎңмқҳ нҷңлҸҷмқ„ нҶөн•ҙм„ң л®Өм§Җм…ҳмңјлЎңм„ң 비м•Ҫн•ң мјҖмқҙмҠӨлӢӨ.мөңмҙҲлЎң н”јм•„л…ёмқҳ м—°мЈј лҸҷмҳҒмғҒмқ„ м—… лЎңл“ңн•ң 2010л…„ мқҙнӣ„, мһҘлҘҙлӮҳ лӮҳлқјм—җ мӮ¬лЎң мһЎнһҲлҠ” мқј м—Ҷмқҙ лӢҳ л“Өмқё кіЎмқ„ м—°мЈјн•ҙ л§җн•ң нӣ„м§Җмқҙн’ҚмқҖ, мҠӨмҠӨлЎңмқҳ нҸ¬н…җм…ңмқ„ м„ұмӢӨн•ҳкІҢ кі„мҶҚ мҰқлӘ…н–ҲлӢӨ.к·ё м–ҙм№ҙмқҙлёҢ(archive)м—җ мқҳн•ҙм„ң м„ңм„ңнһҲ мЎҙмһ¬к°җмқ„ лӮҳнғҖлӮҙкІҢ лҗҳм–ҙ, лҚ°л·” м „л¶Җн„° лӢҳ л“Өмқё мқҙлІӨнҠём—җ м¶ңм—°н•ҳкі кІҪн—ҳмқ„ мҢ“м•„, 2018л…„мқҳ л©”мқҙм Җ кі„м•Ҫнӣ„, мҳӨлҰ¬м§ҖлӮ кіЎмқҳ м •мӢқ лҰҙлҰ¬мҠӨм—Ҷмқҙ мӣҗл§Ё нҲ¬м–ҙгҖҲFujii Kaze “JAZZ&PIANO” The FirstгҖүлҘј мҷ„л§ӨмӢңнӮӨлҠ” л“ұ, мӢ мқёмңјлЎңм„ңлҠ” мқҙлЎҖ н•ңнҺё нҢҢкІ©мқҳ нҳ•нғңлЎң м•„нӢ°мҠӨнҠё нҷңлҸҷмқ„ мҠӨнғҖнҠён•ҳкё°м—җ мқҙлҘҙл ҖлӢӨ.
н•ҙмҷём—җм„ң ліҙнҶөмқҙ м•„лӢҢ мӣҖм§Ғмһ„мқҙ к°җм§Җ лҗҳкё° мӢңмһ‘н•ң кІғмқҖ 2022л…„ 7мӣ”мқҳ мқјмқҙлӢӨ.2022л…„ 10мӣ”м—җ 2 ndм•ЁлІ”мқҳ лҰҙлҰ¬мҠӨлҘј кё°л…җн•ҳлҠ”гҖҲFujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVEгҖүк°Җ 2мқјк°„мңјлЎң 7л§ҢлӘ…мқ„ лҸҷмӣҗн•ҙ, нӣ„м§Җмқҙн’Қмқҙ мӢңлҢҖлҘј лҢҖн‘ңн•ҳлҠ” м•„нӢ°мҠӨнҠёк°Җ лҗң мҲңк°„, 1 stм•ЁлІ” гҖҢHELP EVER HURT NEVERгҖҚмқҳ мҲҳлЎқкіЎ гҖҢмЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ”гҖҚк°Җ TikTokлҘј мӨ‘мӢ¬мңјлЎң нҚјм§Җкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ.к·ё м—ҙмқҖ лӢЁлІҲм—җ нҷ•мӮ°н•ҙ, Spotifyм—җм„ңлҠ” м„ёкі„ 23мқҳ лӮҳлқјмҷҖ м§Җм—ӯм—җм„ң 1мң„лҘј нҡҚл“қ, 2022л…„м—җ н•ҙмҷём—җм„ң к°ҖмһҘ мһ¬мғқлҗң мқјліёмқҳ мқҢм•…м—җ лһӯнҒ¬ мқё н•ҳлҠ” кІғкіј лҸҷмӢңм—җ, мһ¬мғқ нҡҢмҲҳ 2м–өнҡҢлҘј лҸҢнҢҢн•ҳлҠ” л“ұ, мҳҲмғҒмқҙлӢӨлЎң н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ кёҖлЎңлІҢ нһҲнҠёк°Җ лҗҳм—ҲлӢӨ.
кө¬мІҙм Ғмқё кі м°°мқ„ н•ҳкё° м „м—җ, к°ңмқём ҒмңјлЎңлҸ„ гҖҢмЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ”гҖҚмқҳ нһҲнҠёлҠ” мӢ кё°н•ҳлӢӨм—җ мғқк°Ғлҗҳм—ҲлӢӨ.л¬јлЎ гҖҢмЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ”гҖҚлҠ” к·ёмқҳ нҢқ м„јмҠӨк°Җ к· нҳ•мһҲкІҢ нҳ•нғңк°Җ лҗң лӣ°м–ҙлӮң кіЎмқҙл©°, л©ңлЎңл””лӮҳ лҰ¬л“¬лҸ„ мІҳмқҢмңјлЎң л“ЈлҠ” мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ л°ӣм•„ л“Өм—¬м§Җкё° мү¬мҡҙ мәҗм№ҳ-лЎң л¬ҙмһҘн•ҳкі мһҲлӢӨ.к·ёлҹ°лҚ°лҸ„, н•ҳн•„мқҙл©ҙ мҷң мқҙ кіЎмқҙм—ҲлҚҳ кІғмқјк№Ң.к·ё мқҙмң лҠ”, мІӯм·Ёмһҗмқҳ м°ём—¬лҘј мқҙлҒ„лҠ” к°ҖмӮ¬м—җ мһҲлӢӨ.гҖҢм„ёлІҲмқҳ л°ҘліҙлӢӨ л„Өк°Җ мўӢм•„ / л„ҲмҷҖ мқҙлҢҖлЎң м ‘мӢңл°” н• кІҢмқёк°Җ / мЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ” / мЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ”гҖҚлқјкі н•ҳлҠ” ліҙнҺём Ғмқё м •м„ңлҘј лҳ‘л°”лЎң н‘ңнҳ„н•ҳлҠ” к°ҖмӮ¬к°Җ, л¬ҙм–ёк°Җм—җ н–Ҙн•ҳлҠ” мҠӨмҠӨлЎңмқҳ мӮ¬лһ‘мқ„ н‘ңнҳ„н•ҳлҠ”лҚ° к°ҖмһҘ м Ғн•©н•ң нҲҙлЎңм„ң нҢҢм•…н• мҲҳ мһҲм—ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.
мӢӨм ңлЎң мқҙ кіЎмқҙ ліёкІ©м Ғмқё л°”мқҙлһ„мқҙ лҗҳкё° мӢңмһ‘н•ң кІғмқҖ, мһҗмӢ мқҳ мўӢм•„н•ҳлҠ” л¬ҙм—Үмқёк°Җ мқҙ кіЎмқ„ мЎ°н•©н•ң лҸҷмҳҒмғҒмқҙ мң н–үн•ҳкІҢ лҗҳкі лӮҳм„ңлқјкі н•ҳлҠ” м җм—җ мЈјлӘ©н• н•„мҡ”к°Җ мһҲлӢӨ.кІҢлӢӨк°Җ гҖҢмЈҪм–ҙлҸ„ л–јм–ҙ лҶ“м§Җ м•ҠлҠ”лӢӨгҖҚлӮҳ гҖҢмҙқмңјлЎң мҙқкІ©лӢ№н•ң кІғмІҳлҹјгҖҚмқҙлқјлҠ” мҠӨнҠёл ҲмқҙнҠён•ң к°ҖмӮ¬м—җ м№ңмҲҷн•ҙ м ё мҳЁ н•ңкөӯмқём—җ мһҲм–ҙ ліҙл©ҙ, м§ҖкёҲк№Ңм§Җ м—ҶкІҢ мөңм Ғнҷ”лҗң к°ҖмӮ¬мқҙкё°лҸ„ н–ҲлӢӨ.비көҗм Ғ мқҖмң мӨ‘мӢ¬мқҳ к°ҖмӮ¬к°Җ л§ҺмқҖ мқјліёмқҳ мқҢм•…кіјлҠ” лӢ¬лқј, к·ёл ҮкІҢ л§җн•ң гҖҢJ-POPм—җмқҳ мң„нҷ”к°җгҖҚмқ„ ліҙкё° мўӢкІҢ нҡҢн”јн•ҳл©ҙм„ң, нӣ„м§Җмқҙн’ҚмқҖ мғҲлЎңмҡҙ гҖҢкё°нҳёгҖҚлҘј м°ҫм•„ мҡ”кө¬н•ҳлҠ” н•ңкөӯмқҳ SNS мң лӘ©лҜјл“Өмқ„ мҠӨмҠӨлЎңмқҳ н’Ҳм—җ лҒҢм–ҙ л“Өмқҙкі мһҲлӢӨ.
мқҙкІғм—җ к°Җм„ён•ҙ SNSлҘј кё°л°ҳмңјлЎң н•ң көҗл¬ҳн•ң м»Өл®ӨлӢҲмјҖмқҙм…ҳм—җлҸ„ мЈјлӘ©н• н•„мҡ”к°Җ мһҲлӢӨ.мқјліём—җм„ң SNSлҘј нҷңмҡ©н•ң н”„лЎңлӘЁм…ҳмқҙ м„ңм„ңнһҲ ліёкІ©нҷ”н•ҳкё° мӢңмһ‘н–Ҳмқ„ л¬ҙл ө,мһҗкё° мҶҢк°ңлӮҳм•…кіЎ н•ҙм„Өмқҳ лҸҷмҳҒмғҒмқ„ нҲ¬кі н•ҳлҠ” л“ұ, нҢ¬мқҙ мҰҗкёё мҲҳ мһҲлҠ” мҳЁлқјмқё м»Ён…җмё лҘј мһ¬л№ЁлҰ¬ м „к°ңн•ҙ мҷ”лӢӨ.гҖҢмЈҪлҠ” кІғмқҙ мўӢм•„мҡ”гҖҚк°Җ нҸүлІ”м№ҳ м•ҠмқҖ мқёкё°лҘј лӮҳнғҖлӮҙл©ҙ, мҰүмӢң л¬ҙлҸ„кҙҖмқҳ лқјмқҙлёҢ мҳҒмғҒмқ„ YouTubeм—җ нҲ¬кі н•ҙ, X( кө¬Twitter)м—җлҸ„ л©”м„ём§ҖлҘј лӮЁкё°лҠ” л“ұ, к°җмӮ¬лҘј лӮҳнғҖлӮҙлҠ” м Ғк·№м Ғмқё лҰ¬м•Ўм…ҳмңјлЎң мқҙкІғм—җ мқ‘н–ҲлӢӨ.к·ёлҹ¬н•ң м»Өл®ӨлӢҲмјҖмқҙм…ҳмқҙ лӘЁл‘җ мҳҒм–ҙ (лЎң) мқҙлЈЁм–ҙмЎҢлӢӨкі н•ҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқҖ кІ°м •м ҒмқҙлӢӨ.к·ёк°Җ J-POPлқјкі н•ҳлҠ” кіЁмЎ°лЎңл¶Җн„° н’Җм–ҙ л°ңн•ҙ진 гҖҢн•ҙмҷё нҢқмҠӨнғҖгҖҚлЎңм„ңмқҳ нҺҳлҘҙмҶҢлӮҳк°Җ мЈјм–ҙм ё мІңлҜјмқҳ кІғмқҖ, мқҙмҷҖ к°ҷмқҙ л§җмқҳ лІҪмқҙ мҶҢл©ён–Ҳкё° л•Ңл¬ём—җмқҙлӢӨ.мқҙл ҮкІҢ н•ҳкі , гҖҢлҳҗ н•ҳлӮҳмқҳ J-POPгҖҚлҠ” м•„лӢҲкі гҖҢлҳҗ н•ҳлӮҳмқҳ кё°нҳёгҖҚлҘј мҡ”кө¬н•ҳкі мһҲлҚҳ мӮ¬лһҢл“Өмқ„ лҢҖмғҒмңјлЎң н•ҳкі , J-POPмқҳ нҒ¬лҰ¬мӢңлҘј лІ—м–ҙлӮң нӣ„м§Җмқҙн’Қмқҳ мһ‘н’Ҳкіј нҷңлҸҷмқҳ ліём—°мқҳ мһҗм„ёк°Җ ліҙлӢӨ л„“мқҖ мёөмқҳ лҢҖмӨ‘мқ„ мҲҳмӨ‘м—җ л„Јкі мһҲлҠ” лӢҳ м•„мқҙлҘј, мҡ°лҰ¬лҠ” м§ҖкёҲ лӘ©кІ©н•ҳкі мһҲлӢӨ.
мқҙмҷҖ к°ҷмқҙ, мҷ•лҸ„мҷҖ к°ҷмқҙ мғқк°Ғлҗң OTT(мҠӨнҠёлҰ¬л°Қ м„ң비мҠӨ)мҷҖ м •мІҙ мӨ‘мӢ¬мқҳ кёҖлЎңлІҢ м „лһөмқ„ кі„мҶҚ л’Ө집м–ҙ нӣ„м§Җмқҙн’ҚмқҖ мғҲлЎңмҡҙ J-POPмқҳ 진м¶ң м „лһөмқ„ м „к°ңн•ҳкі мһҲлӢӨ.к·ё мЎ°лҘҳк°Җ к¶ӨлҸ„м—җ мҳ¬лқј к·ёмқҳ мқҢм•… м„ёкі„м—җ м№ЁнҲ¬н•ҳкі мһҲлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ, мһҲлӢӨ мҲңк°„, к·ёк°Җ м „н•ҳлҠ” к¶Ғк·№мқҳ л©”м„ём§Җм—җ лҚ”듬м–ҙ л¶ҷлҠ”лӢӨ.к·ёлҠ” гҖҢHigher SelfгҖҚ, мҰү, мһҗм•„лӮҳ мқҙкё°, м§ҲнҲ¬лқјкі н•ҳлҠ” л„Өк°ҖнӢ°лёҢмқё к°җм •мңјлЎңл¶Җн„° н•ҙл°©лҗң мӮ¬лһ‘ к·ё мһҗмІҙлҘј мҶҗм—җ л„ЈлҠ” кІғмқ„, мқҢм•…мқ„ нҶөн•ҙм„ң мһ¬мҙүн•ҳкі мһҲлӢӨ.к·ёлҹ° к·ём—җкІҢ мһҲм–ҙм„ң нҢ¬мқҙлӮҳ кҙҖк°қмқҖ, м–ҙл–Ө лӘЁмҠөмқҙл“ лӘЁл‘җ н•ҳлӮҳмқҙл©°, н•ӯмғҒ к°җмӮ¬н•ҙ, мӮ¬лһ‘н•ҙм•ј н• лҢҖмғҒмқҙлӢӨ.м•„мӢңм•„ нҲ¬м–ҙм—җ мқҳн•ҙм„ң гҖҢмһҗмӢ мқҳ кі н–Ҙк°ҷмқҖ кІғмқҙ н•ңмёө лҚ” нҚјмЎҢлӢӨгҖҚлқјкі л§җн•ҙ NewJeansмқҳ гҖҢDittoгҖҚлҘј м»ӨлІ„н•ҳкұ°лӮҳ н•ңл°ҳлҸ„мқҳ лҜјмҡ”мқё гҖҢнҠёлқјм§ҖгҖҚлҘј мһҗмӢ мқҳ гҖҢ축м ңгҖҚлқјкі мЎ°н•©н•ҙ н”јлЎңн•ҳлҠ” л“ұ, к·ё кіөк°„м—җм„ңл§Ң мЎҙмһ¬н•ҳлҠ” гҖҢм§ҖкёҲгҖҚмқ„ мҶҢмӨ‘нһҲ н•ҳлҠ” лӘЁмҠөлҸ„ лҳҗ, к·ёл ҮкІҢ л§җн•ң гҖҢHigher SelfгҖҚлқјкі лҸҷмқј м„ мғҒм—җ мһҲлӢӨкі л§җн• мҲҳ мһҲмқ„ кІғмқҙлӢӨ.

2024е№ҙгҖҒйҹ“еӣҪгҒ®гғқгғғгғ—гғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгӮ·гғјгғігҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢJ-POPгҒ®жҙ»иәҚгҒҜзӣ®иҰҡгҒҫгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮimaseгҒ®гҖҢNIGHT DANCERгҖҚгҖҒYOASOBIгҒ®гҖҢгӮўгӮӨгғүгғ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ2жӣІгҒ®гғЎгӮ¬гғ’гғғгғҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰJ-POPгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғҲгғ©гғігғҶгӮЈгӮ№гҒҢжө®дёҠгҒ—гҒҹ2023е№ҙгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒжҳЁе№ҙгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®йҹіжҘҪгҒҢжҷ®йҒҚзҡ„гҒӘеҘҪгҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰе®Ңе…ЁгҒ«е®ҡзқҖгҒ—гҒҹе№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒ1е№ҙгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжҙ»зҷәгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹжқҘйҹ“е…¬жј”гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§зү№гҒ«иұЎеҫҙзҡ„гҒӘгӮӨгғҷгғігғҲгӮ’3гҒӨгҒ»гҒ©жҢҷгҒ’гӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒйҹ“еӣҪеҲқгҒЁгҒӘгӮӢJ-POPгғЎгӮӨгғігҒ®гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гҖҺWONDERLIVET 2024гҖҸгҖҒ2ж—Ҙй–“гҒ§2дёҮ5,000дәәгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®иҰіе®ўгӮ’еӢ•е“ЎгҒ—гҒҹYOASOBIгҒ®жқҘйҹ“гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒи—Өдә•йўЁгҒ®е…¬жј”гҒҜеӨ–гҒӣгҒӘгҒ„гҖӮеҪјгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®гӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰеҲқгҒ®й«ҳе°әгғүгғјгғ е…¬жј”гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҖҒJ-POPгҒҢйҹ“еӣҪгҒ®йҹіжҘҪгӮ·гғјгғігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдёҖе®ҡгҒ®и»ҢйҒ“гҒ«д№—гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҗҚе®ҹгҒЁгӮӮгҒ«зӨәгҒ—гҒҹгҖӮ
иҲҲе‘іж·ұгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚJ-POPгғһгғӢгӮўгҒҹгҒЎгҒҢеҪјгҒ®гғүгғјгғ е…¬жј”гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҚҠдҝЎеҚҠз–‘гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғӘгӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’иҰӢгҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҸҚеҝңгҒҜгҖҒгҒҠгҒҠгӮҖгҒӯиҮӘеҲҶгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«еҪјгҒ®гғ•гӮЎгғігҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒ«её°зөҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒеҪјгҒҢж—Ҙжң¬йҹіжҘҪгҒ®гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғјгҒ«гҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҒ«гҒ—гҒҰJ-POPгӮүгҒ—гҒӢгӮүгҒ¬жҙ»еӢ•гҒЁдҪңе“ҒгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҪјгҒҜгҒӘгҒңйҹ“еӣҪгҒ®J-POPгғ•гӮЎгғігҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжҜ”ијғзҡ„йҰҙжҹ“гҒҝгҒҢи–„гҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡжҢҮжҠҳгӮҠгҒ®гӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гӮ№гӮҝгғјгҒ«гҒ®гҒҝй–ҖжҲёгҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгӮӢй«ҳе°әгғүгғјгғ гҒ®гӮ№гғҶгғјгӮёгҒ«з«ӢгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгғ•гӮЎгғігғҷгғјгӮ№гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зӘҒ然з”ҹгҒҳгҒҹз–‘е•ҸгҒ«зӯ”гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҪјгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўгҒӢгӮүиӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢи—Өдә•йўЁгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®зү№з•°зӮ№гӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢиҰӢгҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
д»ҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҹдәӢе®ҹгҒ гҒҢгҖҒеҪјгҒҜYouTubeгҒ§гҒ®жҙ»еӢ•гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгғҹгғҘгғјгӮёгӮ·гғЈгғігҒЁгҒ—гҒҰйЈӣиәҚгҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ гҖӮжңҖеҲқгҒ«гғ”гӮўгғҺгҒ®жј”еҘҸеӢ•з”»гӮ’гӮўгғғгғ—гғӯгғјгғүгҒ—гҒҹ2010е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒгӮёгғЈгғігғ«гӮ„еӣҪгҒ«гҒЁгӮүгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸж§ҳгҖ…гҒӘжӣІгӮ’ејҫгҒҚиӘһгӮҠгҒ—гҒҹи—Өдә•йўЁгҒҜгҖҒиҮӘгӮүгҒ®гғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гӮ’иӘ е®ҹгҒ«иЁјжҳҺгҒ—гҒӨгҒҘгҒ‘гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫҗгҖ…гҒ«еӯҳеңЁж„ҹгӮ’зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғҮгғ“гғҘгғјеүҚгҒӢгӮүж§ҳгҖ…гҒӘгӮӨгғҷгғігғҲгҒ«еҮәжј”гҒ—гҒҰзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгҒҝгҖҒ2018е№ҙгҒ®гғЎгӮёгғЈгғјеҘ‘зҙ„еҫҢгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӣІгҒ®жӯЈејҸгғӘгғӘгғјгӮ№гҒӘгҒ—гҒ«гғҜгғігғһгғігғ„гӮўгғјгҖҲFujii Kaze "JAZZ&PIANO" The FirstгҖүгӮ’е®ҢеЈІгҒ•гҒӣгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒж–°дәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜз•°дҫӢгҒӢгҒӨз ҙж јгҒ®еҪўгҒ§гӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲжҙ»еӢ•гӮ’гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒҷгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҒҫгҒ гҖҒгӮ«гғҗгғјгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жӣІгҖҚгҒ§гғЎгӮӨгғігӮ№гғҲгғӘгғјгғ гҒ«д№—гӮҢгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®з–‘е•ҸгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®з–‘еҝөгӮ’дёҖж°—гҒ«жү•жӢӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгғҮгғ“гғҘгғјжӣІгҒ®гҖҢдҪ•гҒӘгӮ“wгҖҚгҒ гҒЈгҒҹгҖӮиҮӘиә«гҒ®еј·гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгғ”гӮўгғҺжј”еҘҸгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒ«гҖҒR&BгӮ„гғ’гғғгғ—гғӣгғғгғ—гҖҒжӯҢи¬ЎжӣІгҒӘгҒ©гҒ®иҰҒзҙ гӮ’иһҚеҗҲгҒ•гҒӣгҖҒеІЎеұұејҒгҒЁиӢұиӘһгӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒҷгӮӢеҪјзӢ¬иҮӘгҒ®иЁҖиӘһгҒ§жӣІгӮ’зҙЎгҒҺеҮәгҒ—гҒҹжүҚиғҪгҒҜгҖҒеӨ§иЎҶгҒҠгӮҲгҒіи©•и«–家гҒӢгӮүжүӢж”ҫгҒ—гҒ®иіһиіӣгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒҷгҒ®гҒ«еҚҒеҲҶгҒ гҒЈгҒҹгҖӮж—Ҙжң¬з”Јгғ–гғ©гғғгӮҜгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒ®ж–°гҒҹгҒӘйҒ“гӮ’й–ӢжӢ“гҒ—гҒҹе®ҮеӨҡз”°гғ’гӮ«гғ«гҒ®зҷ»е ҙеҪ“жҷӮгҒ«дјјгҒҹеҸҚеҝңгӮӮеӨҡгҒҸгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮе®ҮеӨҡз”°гғ’гӮ«гғ«гҒ®йҹіжҘҪгҒҢеҸҺгӮҒгҒҹжҲҗжһңгҒҢгҖҢж—Ҙжң¬гҒЁгҒ„гҒҶгғӯгғјгӮ«гғӘгғҶгӮЈгҒ®йҷҗз•ҢгҒ®е…ӢжңҚгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғқгӮӨгғігғҲгҒ§жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҪјгҒ®жҲҗжһңгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒеҲ—еі¶гӮ’и¶…гҒҲгҒҰдё–з•ҢгҒ«гӮўгғ”гғјгғ«гҒ§гҒҚгӮӢе®ҢжҲҗеәҰгӮ’иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гҒ«иҮігӮӢгҖӮ
жө·еӨ–гҒ§гҒҹгҒ гҒӘгӮүгҒ¬еӢ•гҒҚгҒҢж„ҹзҹҘгҒ•гӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜ2022е№ҙ7жңҲгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҖӮ2022е№ҙ10жңҲгҒ«2ndгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®гғӘгғӘгғјгӮ№гӮ’иЁҳеҝөгҒҷгӮӢгҖҲFujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVEгҖүгҒҢ2ж—Ҙй–“гҒ§7дёҮдәәгӮ’еӢ•е“ЎгҒ—гҖҒи—Өдә•йўЁгҒҢжҷӮд»ЈгӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢгӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹзһ¬й–“гҖҒ1stгӮўгғ«гғҗгғ гҖҺHELP EVER HURT NEVERгҖҸгҒ®еҸҺйҢІжӣІгҖҢжӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒҢTikTokгӮ’дёӯеҝғгҒ«еәғгҒҢгӮҠгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҖӮгҒқгҒ®зҶұгҒҜдёҖж°—гҒ«жӢЎж•ЈгҒ—гҖҒSpotifyгҒ§гҒҜдё–з•Ң23гҒ®еӣҪгҒЁең°еҹҹгҒ§1дҪҚгӮ’зҚІеҫ—гҖҒ2022е№ҙгҒ«жө·еӨ–гҒ§жңҖгӮӮеҶҚз”ҹгҒ•гӮҢгҒҹж—Ҙжң¬гҒ®йҹіжҘҪгҒ«гғ©гғігӮҜгӮӨгғігҒҷгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҶҚз”ҹеӣһж•°2е„„еӣһгӮ’зӘҒз ҙгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдәҲжғігҒ гҒ«гҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гғ’гғғгғҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
и—Өдә•йўЁгҒ®йҹіжҘҪгҒ«гғқгғғгғ—гғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гҒҢеҚҒеҲҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ жӣІгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҢжӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒ®гғ’гғғгғҲгҒҜдәҲжғіеӨ–гҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮҝгӮӨгҒ®TikTokгғҰгғјгӮ¶гғјгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹзҶұзӢӮгҒҜгғ–гғјгӮҝгғігӮ„гғҷгғҲгғҠгғ гҖҒгғһгғ¬гғјгӮ·гӮўгҒӘгҒ©гӮўгӮёгӮўеҗ„еӣҪгҒёеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҖҒйҹ“еӣҪгҒЁгӮўгғЎгғӘгӮ«гӮӮгҒқгҒ®дҫӢеӨ–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮдёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгӮ·гғ§гғјгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹжӣІгӮ’гӮ№гғҲгғӘгғјгғҹгғігӮ°гӮөгӮӨгғҲгҒ§иҒҙгҒҸгғӢгғҘгғјгғЎгғҮгӮЈгӮўжҷӮд»ЈгҒ®дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮігғігғҶгғігғ„ж¶ҲиІ»гҒ®еӮҫеҗ‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҳ гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҪјгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®гғҗгӮӨгғ©гғ«гғ’гғғгғҲгҒЁжҜ”гҒ№гҒҰзӣёеҜҫзҡ„гҒ«гӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲиҮӘиә«гҒ®гғ•гӮЎгғігғҖгғ гҒ«з№ӢгҒҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҸзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй ҶгӮ’иҝҪгҒЈгҒҰиҰӢгҒҰгҒ„гҒ‘гҒ°гҖҒзөҗеұҖгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚжҘҪжӣІгҒ®еұһжҖ§гҒЁдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йӯ…еҠӣгҖҒSNSдёӯеҝғгҒ®жҙ»еӢ•жҲҰз•ҘгҒҢеҷӣгҒҝеҗҲгҒЈгҒҹеӨ§гҒҚгҒӘгӮ·гғҠгӮёгғјгҒҢдәәж°—гҒ®ж ёгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒӘиҖғеҜҹгӮ’гҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гӮӮгҖҢжӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒ®гғ’гғғгғҲгҒҜдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒҲгҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҢжӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒҜеҪјгҒ®гғқгғғгғ—гӮ»гғігӮ№гҒҢгғҗгғ©гғігӮ№гӮҲгҒҸеҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе„ӘгӮҢгҒҹжӣІгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгӮ„гғӘгӮәгғ гӮӮеҲқгӮҒгҒҰиҒҙгҒҸдәәгҖ…гҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гӮӯгғЈгғғгғҒгғјгҒ•гҒ§жӯҰиЈ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒгӮҲгӮҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒӘгҒңгҒ“гҒ®жӣІгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгғӘгӮ№гғҠгғјгҒ®еҸӮдёҺгӮ’е°ҺгҒҸжӯҢи©һгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢдёүеәҰгҒ®йЈҜгӮҲгӮҠгҒӮгӮ“гҒҹгҒҢгҒ„гҒ„гҒ®гӮҲ / гҒӮгӮ“гҒҹгҒЁгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒҠгӮөгғ©гғҗгҒҷгӮӢгӮҲгҒӢ / жӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸ / жӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҷ®йҒҚзҡ„гҒӘжғ…з·’гӮ’гҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒ«иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢжӯҢи©һгҒҢгҖҒдҪ•гҒӢгҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶиҮӘгӮүгҒ®ж„ӣгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«жңҖгӮӮйҒ©гҒ—гҒҹгғ„гғјгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒ“гҒ®жӣІгҒҢжң¬ж јзҡ„гҒӘгғҗгӮӨгғ©гғ«гҒ«гҒӘгӮҠгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘдҪ•гҒӢгҒЁгҒ“гҒ®жӣІгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеӢ•з”»гҒҢжөҒиЎҢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ«жіЁзӣ®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҖҢжӯ»гӮ“гҒ§гӮӮйӣўгҒ•гҒӘгҒ„гҖҚгӮ„гҖҢйҠғгҒ§ж’ғгҒҹгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮ№гғҲгғ¬гғјгғҲгҒӘжӯҢи©һгҒ«йҰҙжҹ“гӮ“гҒ§гҒҚгҒҹйҹ“еӣҪдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгҒҸжңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹжӯҢи©һгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжҜ”ијғзҡ„гғЎгӮҝгғ•гӮЎгғјдёӯеҝғгҒ®жӯҢи©һгҒҢеӨҡгҒ„ж—Ҙжң¬гҒ®йҹіжҘҪгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҖҢJ-POPгҒёгҒ®йҒ•е’Ңж„ҹгҖҚгӮ’иҰӢдәӢгҒ«еӣһйҒҝгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒи—Өдә•йўЁгҒҜж–°гҒҹгҒӘгҖҢеҘҪгҒҝгҖҚгӮ’жҺўгҒ—жұӮгӮҒгӮӢйҹ“еӣҪгҒ®SNSгғҺгғһгғүгҒҹгҒЎгӮ’иҮӘгӮүгҒ®жҮҗгҒ«еј•гҒҚеҜ„гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҖҒSNSгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҹе·§гҒҝгҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ«гӮӮжіЁзӣ®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§SNSгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгғ—гғӯгғўгғјгӮ·гғ§гғігҒҢеҫҗгҖ…гҒ«жң¬ж јеҢ–гҒ—гҒҜгҒҳгӮҒгҒҹй ғгҖҒиҮӘе·ұзҙ№д»ӢгӮ„жҘҪжӣІи§ЈиӘ¬гҒ®еӢ•з”»гӮ’жҠ•зЁҝгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгғ•гӮЎгғігҒҢжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігӮігғігғҶгғігғ„гӮ’гҒ„гҒЎж—©гҒҸеұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»гҒ¬гҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҖҚгҒҢдёҰгҖ…гҒӘгӮүгҒ¬дәәж°—гӮ’зӨәгҒҷгҒЁгҖҒгҒҹгҒ гҒЎгҒ«жӯҰйҒ“йӨЁгҒ®гғ©гӮӨгғ–жҳ еғҸгӮ’YouTubeгҒ«жҠ•зЁҝгҒ—гҖҒXпјҲж—§TwitterпјүгҒ«гӮӮгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’ж®ӢгҒҷгҒӘгҒ©гҖҒж„ҹи¬қгӮ’зӨәгҒҷз©ҚжҘөзҡ„гҒӘгғӘгӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігҒ§гҒ“гӮҢгҒ«еҝңгҒҲгҒҹгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒҢе…ЁгҒҰиӢұиӘһгҒ§гҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҜжұәе®ҡзҡ„гҒ гҖӮеҪјгҒҢJ-POPгҒЁгҒ„гҒҶжһ зө„гҒҝгҒӢгӮүи§ЈгҒҚж”ҫгҒҹгӮҢгҒҹгҖҢжө·еӨ–гғқгғғгғ—гӮ№гӮҝгғјгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғҡгғ«гӮҪгғҠгӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҲгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҖи‘үгҒ®еЈҒгҒҢж¶Ҳж»…гҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®J-POPгҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®еҘҪгҒҝгҖҚгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹдәәгҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒJ-POPгҒ®гӮҜгғӘгӮ·гӮ§гӮ’и„ұгҒ—гҒҹи—Өдә•йўЁгҒ®дҪңе“ҒгҒЁжҙ»еӢ•гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢгӮҲгӮҠеәғгҒ„еұӨгҒ®еӨ§иЎҶгӮ’еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгӮ’гҖҒжҲ‘гҖ…гҒҜд»Ҡзӣ®ж’ғгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзҺӢйҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҹOTTпјҲгӮ№гғҲгғӘгғјгғҹгғігӮ°гӮөгғјгғ“гӮ№пјүгҒЁгӮҝгӮӨгӮўгғғгғ—дёӯеҝғгҒ®гӮ°гғӯгғјгғҗгғ«жҲҰз•ҘгӮ’иҰҶгҒ—гҒӨгҒҘгҒ‘гҖҒи—Өдә•йўЁгҒҜж–°гҒҹгҒӘJ-POPгҒ®йҖІеҮәжҲҰз•ҘгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®жҪ®жөҒгҒ®жіўгҒ«д№—гҒЈгҒҰеҪјгҒ®йҹіжҘҪдё–з•ҢгҒ«жөёйҖҸгҒ—гҒӨгҒӨгҒӮгӮӢдәәгҖ…гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзһ¬й–“гҖҒеҪјгҒҢдјқгҒҲгӮӢ究жҘөгҒ®гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒ«иҫҝгӮҠгҒӨгҒҸгҖӮеҪјгҒҜгҖҢHigher SelfгҖҚгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒиҮӘжҲ‘гӮ„еҲ©е·ұгҖҒе«үеҰ¬гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гҒӘж„ҹжғ…гҒӢгӮүи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҹж„ӣгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒйҹіжҘҪгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰдҝғгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҪјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгғ•гӮЎгғігӮ„иҰіе®ўгҒҜгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘе§ҝгҒ§гҒӮгӮҢзҡҶдёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеёёгҒ«ж„ҹи¬қгҒ—гҖҒж„ӣгҒҷгҒ№гҒҚеҜҫиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮёгӮўгғ„гӮўгғјгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®гҒөгӮӢгҒ•гҒЁгҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒ•гӮүгҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҖҒNewJeansгҒ®гҖҢDittoгҖҚгӮ’гӮ«гғҗгғјгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжңқй®®еҚҠеі¶гҒ®ж°‘и¬ЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгғҲгғ©гӮёгҖҚгӮ’иҮӘиә«гҒ®гҖҢгҒҫгҒӨгӮҠгҖҚгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰжҠ«йңІгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®з©әй–“гҒ§гҒ®гҒҝеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖҢд»ҠгҖҚгӮ’еӨ§дәӢгҒ«гҒҷгӮӢе§ҝгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҖҢHigher SelfгҖҚгҒЁеҗҢдёҖз·ҡдёҠгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
е…Ҳиҝ°гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒи—Өдә•йўЁгҒ®дҪңе“ҒгӮ’еҚҳзҙ”гҒ«гҖҢJ-POPгҖҚгҒЁеҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜз„ЎзҗҶгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеӨ§иЎҶгҒҢе…ұж„ҹгҒ§гҒҚгӮӢгғқгғ”гғҘгғ©гғјгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҖҒе…Ёдё–з•ҢгҒ®дәәгҖ…гӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҹж°—гҒ•гҒҸгҒ§еҝғгҒ®гҒ“гӮӮгҒЈгҒҹгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒйҒҺеҺ»гҒ§гӮӮжңӘжқҘгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖҢд»ҠгҖҚгӮ’з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢж„ҹжғ…гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁиӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒдәәз”ҹгӮ’гӮҲгӮҠеәғгҒ„иҰ–зӮ№гҒ§иҰӢгҒӨгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дҝғгҒҷгӮўгғҶгӮЈгғҒгғҘгғјгғүгҒҫгҒ§гҖӮзҹҘгӮҢгҒ°зҹҘгӮӢгҒ»гҒ©и—Өдә•йўЁгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢгҖҢJ-POPгғ–гғјгғ гҖҚгҒ®жҪ®жөҒгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜжҚүгҒҲгҒҚгӮҢгҒӘгҒ„еӯҳеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮйқ’жҳҘгҒҜе„ҡгҒ„гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒгҒқгҒ®ијқгҒҚгҒӢгӮүзӣ®гӮ’йҖёгӮүгҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҖҢйқ’жҳҘз—…гҖҚгҒ®жӯҢи©һгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒи—Өдә•йўЁгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еӣҪеўғгӮ’и¶…гҒҲгҖҒгҖҢгғқгғғгғ—гӮўгӮӨгӮігғігҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«йҷҚгӮҠжіЁгҒҗгҒҫгҒ°гӮҶгҒ„е…үгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгӮӢгҒ§д»Ҡж—ҘгҒ®дёҖж—ҘгӮ’еҠӣгҒ„гҒЈгҒұгҒ„зң©гҒ—гҒҸијқгҒҚгҒҚгҒЈгҒҰгҖҒжҳҺж—Ҙж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгӮӮиӘ°гӮӮдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгӮҸгҒӘгҒ„е…үгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ
<iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/QPLviaYkuSs" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe>